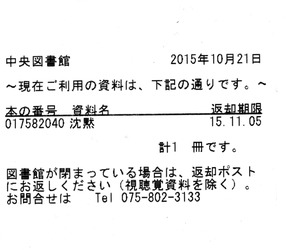 祭司ロドリゴが、転向した師のフェレイラと再会し日本語で会話するシーンで、小学生くらいの頃にやはり一度は「沈黙」を読んだことを思い出した。そのシーンで抱いた不自然さの感覚が蘇ってきた。しかしもちろん、ポルトガルからやってきて日本に潜入するロドリゴがたいした障壁もなく日本語(しかも長崎弁)を理解する「感じ」で最初から描かれており、かといって日本語のまれな熟達者という説明があるわけでもなく、さらに後半では幕府が彼のために用意する通訳が登場するのだが、錯綜しているように見える設定の辻褄は読者の想像のうちに合わせてくれということなのかもしれないけど、ここは多少なりとも忍耐を要求すると思う。
祭司ロドリゴが、転向した師のフェレイラと再会し日本語で会話するシーンで、小学生くらいの頃にやはり一度は「沈黙」を読んだことを思い出した。そのシーンで抱いた不自然さの感覚が蘇ってきた。しかしもちろん、ポルトガルからやってきて日本に潜入するロドリゴがたいした障壁もなく日本語(しかも長崎弁)を理解する「感じ」で最初から描かれており、かといって日本語のまれな熟達者という説明があるわけでもなく、さらに後半では幕府が彼のために用意する通訳が登場するのだが、錯綜しているように見える設定の辻褄は読者の想像のうちに合わせてくれということなのかもしれないけど、ここは多少なりとも忍耐を要求すると思う。
ロドリゴが踏み絵を踏んだのは、おもには、彼への連帯責任のような形で拷問にあわされている信徒たちを祈りでは救えない(神は沈黙していて奇跡を起こさない)と断念したからであり、この断念が「奇跡の不存在」の確信を意味するわけでは全然ないとしても、彼の信仰からある一般的な無邪気さを切除するかもしれない。しかし、迫害と殉教者に満ちたキリスト教の長い歴史から見て、この断念はどの程度の「負い目」だろうか。
眼の前の踏み絵が、(聖画として)異教徒が作ったまがいものであり、しかるにそれを踏んで信徒たちを救うことはキリスト教的な倫理にまったく整合し、ロドリゴの信仰における元々の立場にもなんらの異変が生じているわけではないとしても、現に「それ」を踏んでしまった事実の生々しさが彼の宗教的な純粋さをいやらしく腐食させ、戻れない孤独に陥れてゆく。
一昨年のクリスマスにも書いたけど、キリスト教は偶像崇拝の否定について一定の欺瞞というべきか自己矛盾を抱えていると思う。そしてそれは、(キリスト教だけがどうとかいう問題ではなく)人間の抽象化能力の限界みたいなものと関係しているかもしれない。母子像やイコンやロザリオに本質的な意味があるわけではない、と宗教者がいくら説いたところで、人々はそれを求め愛着しようとする。そのぬぐいがたい物体性への希求みたいなものが、それを理論的に乗り越え得たように思い過ごしている誰かにおいてすら、逆流し、たとえば「踏んだ足」に心身症のような痛みを生じさせるかもしれない。
いわゆる、日本に入ってくる様々な宗教が奇妙な「日本化」を遂げて変質してしまう、というテーマも伏流のようにして主張されるのだが、海にしつらえた杭にキリスト教徒たちを縛り付けて潮の満ち引きで衰弱死(水死?)させる処刑方法にもその意志が象徴されていると思う。
自然が、人による超越的な措定をすべてかき消してしまう。
言葉が自然を乗り越えない。
たぶん、日本人の自然への畏怖は、自然に対する感謝と裏腹だ。だから単に自然に超越性を認めて怯えているのではなく、ある倫理性を帯びている。もっと言えば、そこからの自動的な恩恵がなくなった時日本人の精神性に根底的な変化が訪れうるのではないかと思うが、幸か不幸か日本の風土はかなり恵まれている。
「パードレ、お前らのためにな、お前らがこの日本国に身勝手な夢を押しつけよるためにな、その夢のためにどれだけ百姓らが迷惑したか考えたか。見い。血がまた流れよる。何も知らぬあの者たちの血がまた流れよる」『沈黙』(p211 新潮文庫)
遠藤周作
追記(2015/12/27):
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。JHON 1:1

コメントする