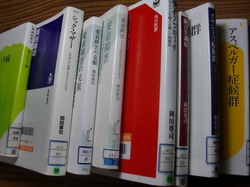 岡田尊司の著作を集中的に読んでいる。
岡田尊司の著作を集中的に読んでいる。
アタッチメント(愛着)は対象関係論でもよく出てくる話題だが、より推し進めて、アタッチメントを正常化することで様々な疾患が治ると主張する作家の代表格が京都医療少年院で診ておられた岡田尊司氏。
少年院での治療費用は子供たちが支払うわけではもちろんないわけで、間接的ながらも「無償の愛」としての代理安全基地がまだ成り立つ時期である。岡田氏はこの「愛着アプローチ」が成人患者にも効くと主張しているのだが、その点、やや留保的な印象を持った。
患者の主観的世界を一方的に受容する態度はコフートのやり方に似ている感じがした。同時に彼の変容性内在化に到達させ得なかった症例が思い出される。
あと、本格的な精神病などでこのやり方で間に合う感じがあんまりしなかった。
しかしながら、仮に劇的に効かなくとも、(家族関係を起源とする)問題の本質を大づかみするという意味で、「愛着アプローチ」は知っておいて損はないかも。回避性人格障害や境界性人格障害、自己愛性人格障害等がたびたび言及される。
アタッチメントはその人物の幼児的全能感の保管庫のようなものだと思う。真の実態が幻想なのだとしても(!)、その幻想がないと大抵の人は前に進めない。
追記(2020/07/23):
調べるとネット上には岡田氏への批判があって、さもありなんという感じなのだが、一応擁護のようなことをしておくと、「反応性愛着障害」や「脱抑制型対人交流障害」のような公的な愛着障害の概念を独自に敷衍していることは、彼自身が著作の中である程度説明している(少なくともそういう箇所がある)。もちろんそのような拡大が正しい行為かどうかは是非があるのだろうが、私は読み始めに手持ちのDSM5と比較し明らかな個人の主張と認識していたので、当初よりそういう立場・思想の人なのだろうという受け止めである。
愛着対象の代理としてカウンセラーを据えるやりかたは、誰が考えても依存を生む。一生責任を持つような心構えを岡田氏は披露していたが、治療は経済行為でもあるのだから見方によっては白々しく感じなくもない。
あと、こじれた親子関係を仲裁・適正化することが、彼の著作上に繰り出す症例のようにうまくいくのか相当訝しい。
ただ、私は、岡田氏を詐欺師のように表現することには(今のところ)賛同しない。愛着の形成や様式あるいはその発展の仕方が人間の精神に致命的な影響を与えるという主張には、大づかみの論理的一貫性があると思うからだ。
追記2(2020/08/03):
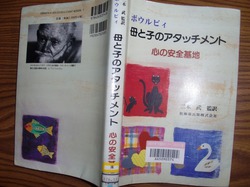 愛着理論の確立者であるボウルビィを読んだほうが早いかも(ただし訳はあまり良くない)。
愛着理論の確立者であるボウルビィを読んだほうが早いかも(ただし訳はあまり良くない)。
追記3(2020/08/22):
追い岡田尊司をしているのだが、『ADHDの正体』(p45下段真ん中)の記述が意味不明で、もとの論文に当たると、おそらく不注意型のパーセンテージのことを岡田氏が誤解されているのだと思う。全文を見れば結果をまとめた表があり、51.7%なのは子供時代もADHDだった大人ADHDが不注意型である割合であり、54.1%の方は子供時代にはADHDでなかった大人ADHDの中での不注意型の割合であると思われる。
追記4(2020/09/20):
岡田氏の著作を第二波的に読んでいて、今図書館で予約してる「死に至る病」で7月から数えて18冊目になるのだが、未だに岡田氏の印象は微妙なままである。しかし刺激を受けるという次元ではポジティヴな印象を持っている。
追記5(2020/09/26):
なんだかいつもとトーンが違う。
自己肯定感を持ちなさい、などと、いい年になった人たちに臆面もなく言う専門家がいる。が、それは、育ち盛りのときに栄養が足りずに大きくなれなかった人に、背を伸ばしなさいと言っているようなものだ。岡田尊司『死に至る病』(p20)

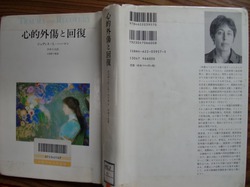
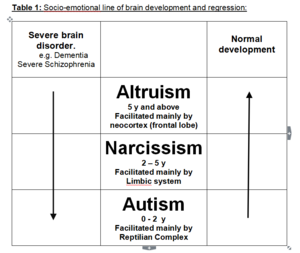

最近のコメント
purplebaby≫momoさん 不具合確認しました。 原因は調査中ですが、… (250610)
momo≫いつも活用させていただきありがとうございます。最近、「通信エ… (250610)
purplebaby≫MOさん Youtubeは、自動生成系の字幕の場合、複数の… (240325)
MO≫いつもありがたく使用させていただいています。 不具合なのか1… (240324)
purplebaby≫2023/10/16 15:49 コメント投稿者: 山田 隆… (231016)
MO≫はじめまして、便利で毎回使用させていただいていますが、1点リ… (230515)
wakamin≫もう何年も利用させていただいております。 srtだけでなく、… (230127)
sennapeng≫YouTubeの英語字幕を、ゆっくり翻訳できないかとググって… (220519)
tab≫初めて利用させて頂きました。 無料で公開してくださり本当にあ… (220507)
purplebaby≫イナチャン55さん、yosiさん、動作報告ありがとうございま… (211205)