・エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』 東京創元社
ルネサンスは地中海貿易でいち早く豊かになったイタリアから欧州に広がったわけだが、さらなる資本主義の進行により教会が腐敗しその反動としてルターやカルヴァンが登場してプロテスタントが生まれた。欧州の人々は経済・社会的な地殻変動によってしばらく生き方の方向性を見失ったが、かなりの勢力が新たな帰属先としてプロテスタント信仰と資本主義的な価値観が絡み合ったような社会システムを構築し普及させていった。ある意味なんでもないような過程であるが、フロムはサディズムやマゾヒズムといった概念を駆使してこれに対し独自の説明を展開する。
歴史のはざまに落ち込み方向性を見失った人々に対して、フロムは、何かに従う(マゾヒズム)のではなく自発的に生きることを要求するのだが、無謀な飛躍を含むというかより強い言葉を使えば欺瞞のようなものを感じざるを得ない。人はそんなに強くないし、未来や合理性に関し十分に予見的でもない。
当たり前だが、なにか(価値観や関係性や集団)に従おうとするのはそれだけでは別にマゾヒズムではない。たとえば、見知らぬ土地に旅行に行って不案内だからとガイドを雇ったとして、情報の真偽は確かめようがないけれどお金も払ってるし大体ガイドの言うことに従うのが普通だと思われるが、もちろんこれもマゾヒズムではない。歴史の変動期に翻弄された人々は、このような見知らぬ土地に迷い込んだ人に似ているだろう。
たとえば、現代的な愛着理論の被虐待児に対する観察で、健全な愛着を得られなかった乳幼児たちは、本来愛着的なシチュエーションであっても無反応か無秩序な反応をする。このような事態は自発的に生きるための方向性を(ほとんど半永久的に)失わせる。愛着対象を内在化できている健康な幼児は、自分のある種の行為が親から愛される行為であることを知って、そのことが彼らの自発性に実効的な形式を与えてゆく。
つまり自発性は、当人が無意識だとしても、程よい母親(とのコミュニケーション)によって早期に刻み込まれたある方向付けが大部を占める。そして、その方向づけが後に実際に社会的な果実を当人にもたらすならば、その人はそのままスムーズに人生を歩めていると見なせるだろう。歴史的な変動期には、この人生早期の方向付けと自立後の現実との間にズレが生じやすくなる。しかしながら、これはフロムが「自動人形」として描くような、心の基礎部分が壊れたような、病的な状態でないことは言うまでもない。そこまでサシが深く重篤であるためには、上述のように早期の愛着獲得に失敗している必要がある。当時の大衆層がみんなそのように病的な心的基礎を持っていたとは思えない。フロムのある種の無分別がこの辺りに隠れていると思われるが、また、個人の病理に関する知識を集団に当てはめるために生じる齟齬の一種だとも言えるかもしれない。
歴史の転換点では人々の古いやり方が壊滅し、跳び移る石が必要になるわけだが、いつでも都合よく願望に叶うものが見つかるわけではないだろうし、状況は様々だ。プロテスタントとナチズムの同次元での対比はその意味でもかなりの違和感を残す。
本書のおおまかな主題はナチズム成立の原因を探ることにあると思われるが、宗教改革前後の大衆の中世カトリックからプロテスタントへの乗り換えが前半に描かれ、大きな伏線となっている。同様の依存の移行として大衆のナチズムへの傾倒があったと言いたいわけである。ただ、カトリック国のイタリアでも類似のファシズムは台頭したし、日本でも伝統的な天皇を中心とした独特なファシズムかそれに近いものが現れた。フロムは、当時の資本主義の先進国に対し共通して一歩か半歩遅れを取っていたこれらの国々を相互に比較するようなことはしていない。
不満を持った社会階層や国民が団結したりその代表者が攻撃的(サディズム的!?)になることは、私にはちっとも不思議じゃない。かなり当たり前の反応である。にも拘らず、フロムは何か、不当にも降って湧いた奇異な事態であるかのようにこれを叙述するような感じがある。
フロムの考える自由は、深刻な社会変化に対して十分なレジリエンスを発揮できるほどに愛着関係に恵まれた個人の生き方を遠いモデルにしているようにも思われる。そういう人は、社会や身の回りに根底的な変化が生じても、相当な程度適応する力があるわけだが、誰でもそのように高度なレジリエンスを持ち合わせているわけではもちろんないし、乳幼児期までに培われている可能性が高く、大人になってからそれを獲得するのはかなり難しいことのように思われる。
フロムは(社会的に成功した)芸術家を自発性を発揮する羨望すべき存在として提示するが、留保したいところだ。内的な自発性と外的な成功の法則があらかじめ合致しているような人が世の中にいるとしても、その人物がこの世界を生み出したのでないとすれば、機序の本体は必ず現実の側にある。彼はたまたま自己中心の夢から醒めないままでいられているに過ぎない。仮に一生涯醒めないままでいられるケースがあったとしても、中間をゴールと取り違えたままでい続けることであり、それはそれで一つの悲劇かもしれない。
しかも実際の芸術家は需要に合わせるため秘密裏に様々な調整をしているに違いなく、それは水鳥の水面下の足掻きのようなものだと思われる。
芸術家の自発性というものは、理想的な成熟による自己確立とは別のものであるように、私には思われる。
ただフロムは称揚しながらも、これを子供の自発性の美しさと併置してもおり、どこかでは未熟なものと分かっているのかもしれない。むしろ内面と外界のずれにどう対峙するかが成熟した自発性の領分であろう。
名著と言われる本書を読みながら、この作品がどうしてそのような強い力を読者に及ぼすことができるのか、原因を考えないではいられなかった。エーリッヒ・フロムは、この著作において、自発性というものを肯定するモチーフを徹底的に強調しその上に論を展開している。人の自発性を(極端なほどに)強調するということは、読者に対してどうしたって各々の「いま、ここ」を意識させることになる。読めば読むほど、外部に制限されない生の自己というものを読者自身に突きつける。このことが、いわゆるマインドフルネスと同じ効果をもたらすのではないかと思われるのである。禅もある種のマインドフルネスである。外的な刺激や束縛を忘れて、本来の自分というものをひととときでも取り戻す。
そういうわけで、本書の内容であるナチズムの原因や成立についての説明がどこまで厳密なものであるかはさておき、読者に対してメンタル的にポジティヴな効果をもたらす可能性があり、そのことが読後感をいやが上にも爽快なものにする直接の原因になっているのではないかと思われるのだ。
ただ、現実的には、人は自発的でばかりもいられない。土日の坐禅会でリフレッシュしたサラリーマンが月曜からはまた会社でもがくことになるように、この本を読み終えてしばらくはその薬効に与るとしても、読者は共同性から逃れられない現実に帰っていかなければならない。
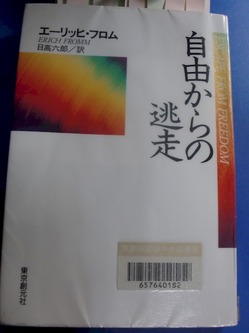 p.21
p.21『本書で提出した立場は、フロイトの考えとはちがっている。フロイトは歴史というものを、社会的には規定されない心理的な要素の結果であると説明したが、われわれはそれに強く反対する。また、社会過程における動的な要素の一つである人間的な要素の役割を無視するような理論にも、強く反対する。』
※フロイトがそんな極端な立場だっただろうか?
p.53
『近代的な意味での自由はなかったが、中世の人間は孤独ではなく、孤立してはいなかった。生まれたときからすでに明確な固定した地位をもち、人間は全体の構造のなかに根をおろしていた。こうして、人生の意味は疑う余地のない、また疑う必要もないものであった。人間はその社会的役割と一致していた。かれは百姓であり、職人であり、騎士であって、偶然そのような職業をもつことになった個人とは考えられなかった。社会的秩序は自然的秩序と考えられ、社会的秩序のなかではっきりした役割を果せば、安定感と帰属感とがあたえられた。そこには競争はほとんどみられなかった。ひとは生まれながら一定の経済的地位におかれ、それによって、伝統的に定められた生活程度は保証されたが、同時に、より高い上層階級の人間にたいする経済的義務は果たさなければならなかった。しかしこのような社会的地位の限界を破らないかぎり、自由に独創的な仕事をすることも、感情的に自由な生活をすることも許されていた。いろいろな生活様式をあれこれと自由に選ぶという、近代的な意味での個人主義(しかしこの選択の自由は非常に抽象的なものであるが)は存在しなかったが、実際生活における具体的な個人主義は大いに存在していた。』
※しかしながら、有能とはいえない職人の分不相応な自負心のようなものも想起させる。人々が共通の基準では試されなかった時代だったかもしれないが、そういう状況下で見出された個人主義は現代から見れば幻影のようなものかもしれない。個人としての夢の中に居られた時代だったのだ。
p.93
『ひとは自分が自らの主人であるとは考えてはならない、とかれは教える。』
※カルヴァンの教えだが、腐敗した教会を介さずに、神に直接対峙して自己否定する態度はルターと共通している。
p.97
『カルヴィニストはまったく素朴に、自分たちは選ばれたものであり、他のものはすべて神によって罰に決定された人間であると考えた。』
※しかし人に対してはこのような尊大さが共存する。ルターの権威主義とも通底するが、ある種の差別感情が宗教改革の原動力だったことは否めないようだ。ルターは大衆というものを相当嫌悪したようだ。
p.138
(資本主義がプロテスタンティズムの精神をさらに発展させた文脈で)
『財産や社会的名声をほとんどもたない人間にとっては、家族が個人的威光を与える源であった。そこでは個人は「なんらかのもの」と感ずることができた。かれは妻や子供をしたがえ、舞台の中心となることができた。そして単純にも自分の役割を自然の権利と考えていた。かれは社会的世界では無に等しいが、家庭では国王であった。家族のほかに、国家的な誇り(ヨーロッパではしばしば階級的誇り)がまた重要な意味をあたえた。個人的には無に等しくても、自分の属している集団が、同じような他のしゅうだんよりも優れていると感ずることができれば、それを誇ることができた。』
※図らずもナルシシストの説明とほぼ同じだが、私的に実在する具体的な人物を想起した。
p.164
『かれは彼女なしには、―あるいはすくなくとも、かれの掌中にあって頼りない存在と思われるような人間なしには生きていけない。ただこの関係が破れそうなときにだけ、愛の感情があらわれる。他のばあいには、サディズム的人間は、かれが支配していると感じている人間だけをきわめてはっきりと「愛し」ている。』
※これもナルシシストの説明である。
p.170
『マゾヒズム的努力のさまざまな形は、けっきょく一つのことをねらっている。個人的自己からのがれること、自分自身を失うこと、いいかえれば、自由の重荷からのがれることである。』
※自由の重荷というより現実の重荷ではないか。
p.175
『サディズム的衝動の本質はなんであろうか。ここでもまた、他人に苦痛をあたえようという願望が本質なのではない。サディズムの形にはさまざまなものが観察できるが、それはただ一つの本質的な衝動にまでさかのぼることができる。すなわち他人を完全に支配しようとすること、かれをわれわれの意志にたいして無力な対象とすること、かれの絶対的支配者となること、かれの神となり、思うままにかれをあやつることである。かれを絶滅させ、彼を奴隷にするのは、この目的のための手段である。その最もきびしい目標はかれを悩ませることである。なぜなら他人を支配する力として、他人に苦痛をあたえ、自己防禦できないものに苦悩をしのばせる以上のことはないからである。他人(あるいは他の生物)を完全に支配することの快楽、これがサディズム的衝動の本質である。』
※素行障害の少年の小動物への嗜癖的な殺傷や、サイコパスの起こす快楽的な犯罪など、サディズムが必ずしも社会関係としての支配を求めているわけではないケースは多々ある。口唇期サディズム。
p.192
『またかれらは、依存しているという事実を全然意識しないこともよくある。たとえこのような依存をぼんやりと意識しているとしても、かれらが依存している人間や力は曖昧なままになっていることが多い。この力に結びつくはっきりしたイメージはない。その本質的な性質は、ある人間を保護し、助け、発展させ、彼らとともにあり、彼らを孤独にしないような働きをするところにある。このような性質を持つ「X」を魔術的な助け手と呼ぶことができよう。』
※カレンホーナイが著書「自己分析」の中で『魔術的救助』とか『魔術的援助』と呼んだものと類似だが、出版はフロムのほうが一年早いようだ。こういう表現の仕方の起源が他にある可能性もあるが未知。現実世界から漏れ出した自己愛の痕跡かもしれない。養育過程になんらかの深い欠損がある場合、こういう心理は簡単に克服できるようなものではない。
p.233
『ナチズムの諸原理にたいしてどんなに反対していようとも、もしかれが孤独であることと、ドイツに属しているという感情をもつことと、どちらか選ばなければならないとすれば、多くのひとびとは後者を選ぶであろう。』
※ドイツ人フロムは本書執筆時(1941)にはアメリカに移住してすでに何年も経っている。現実にはナチズムに対して明確な否定的意識を持っていたドイツ人はごく少数だったろう。
p.234
『下層中産階級の社会的性格が労働者階級のものとことなっていたといっても、それはこの性格構造が労働者階級のうちには存在しないということではない。しかしそれは下層中産階級に典型的なものであって、労働者階級ではこの同じ性格構造を同じように明瞭に示したものは、ほんの少数であった。』
※なんとも妖しい言い回しである。ある社会的階級に顕著な特徴が別の階級にあまり見られないことは当たり前で、ほとんどトートロジーのようなものである可能性もある。また精神に内在化したものではなく、単にある階級に共通する外的な条件を反映したものにすぎない可能性もあるだろう。
p.244
『サディズムは他人にたいして、多かれ少なかれ破壊性と混合した絶対的な支配力をめざすものと理解され、マゾヒズムは自己を一つの圧倒的に強い力のうちに解消し、その力の強さと栄光に参加することをめざすものと理解される。サディズム的傾向もマゾヒズム的傾向もともに、孤立した個人が独り立ちできない無能力と、この孤独を克服するために共棲的関係を求める欲求とから生ずる。』
※幼児性が残存したものであることは疑いがないとは思う。
p.245
『ゲッペルスは、サディズム的人間が自己の対象に依存するさまを正確に描いている。すなわち、サディズム的人間は他のだれかに対して力をもたないかぎり、どんなに弱く空虚に感ずるか、またこの支配力がどんなにかれに新しい力をあたえるかを描いている。「ひとはときに深い意気消沈にとらえられることがある。ひとは再び大衆の前にでるときにのみそれを克服することができる。民衆はわれわれの力の源泉である」。』
※これも自己愛で説明したほうが早いが、権力者等に付随して起こりうる一般的な現象でありナチスに特有なものでもなんでもない。
p.248
『自分の目的はドイツの繁栄だけでなく、文明一般の最良の利益に奉仕しているのだというヒットラーの確信は、この数年来あらゆる新聞読者に周知のことであった。』
※ポツダム宣言では日本が「世界征服」を企んでいたことになっているのだが、多分知っている日本人は殆どいない。現実はせいぜい大東亜共栄圏の構築であろうか。ただこの記述は「我が闘争」からのようなので事実であろう。合理化された誇大感として捉えればどうということもない。
p.253
『サド・マゾヒズム的性格に典型的な、強者にたいする愛と無力者にたいする憎悪は、ヒットラーやかれの追随者の非常に多くの政治的行動を説明する。』
※このサド・マゾヒズム的性格という謎めいた語彙はナルシシストにきわめてスムーズに置き換えられる。
p.267
『近代人にたいする自由の二面性を論じたとき、現代において、個人の孤独と無力を増大させている経済的諸条件を指摘した。すなわちその心理的結果を論じて、この無力は権威主義的性格にみられる一種の逃避を導くか、あるいは孤独となった個人が自動人形となり、自我を失い、しかも同時に意識的には自分は自由であり、自分にのみ従属していると考えるような強迫的な画一性に導くことを示した。』
※小市民的な幸福を全否定しているようにも読める。フロムの傲慢さが垣間見える。
p.269
『他方、子どもは教育の早い時期に、まったく「自分のもの」でない感情をもつように教えられる。とくに他人を好むこと、無批判に親しそうにすること、またほほえむことを教えられる。』
※本書でかなりぞっとした箇所。大丈夫ですかフロムさん?
p.279
『近代史が経過するうちに、教会の権威は国家の権威に、国家の権威は両親の権威に交替し、現代においては良心の権威は、同調の道具としての、常識や世論という匿名の権威に交替した。われわれは古い明らさまな形の権威から自分を解放したので、新しい権威の餌食となっていることに気がつかない。われわれはみずから意志する個人であるというまぼろしのもとに生きる自動人形となっている。』
※フロムには共同性に対する過剰な潔癖症が表れる。ナチズムに対する反発が底流にあるのかもしれないが、もはや極論に近くなっている。
p.281
『風変わりにならず、他人の期待に順応することによって、自己の同一性についての懐疑は静められ、一種の安定感があたえられる。しかしその払う代価は高価である。自発性と個性を放棄することは生命力の妨げとなる。心理的に自動人形であることは、たとえ生物学的には生きていても、感情的、精神的には死を意味する。たとえ生の運動をおこなっているとしても、かれの生命はかれの手から砂のようにこぼれていく。』
※共同性によって独りでは決して得られないものが得られるわけだが、共同性にのみこまれてしまうかどうかは別の話だし、ほとんどの人は何らかの距離を取って生きているはずなのである。ペルソナ等。
p.286
『芸術家の地位は傷つきやすいものである。というのは、その個性や自発性が尊敬されるのは、じっさいには成功した芸術家だけであるから。もし作品が売れなければ、かれは隣人から奇人か「神経症患者」とみられる。芸術家のこのような事情は、歴史上の革命家の事情とにている。せいこうした革命家は経世家となり、失敗した革命家は罪人となる。』
※芸術家の恣意性は受け手の現実法則と合致した場合のみ価値を持つ。芸術家がこの世界の創造主である可能性はほぼゼロなので、それはなんらかの偶然かめぐり合わせによってもたらされるにすぎない。
p.288
『自発的に行動できなかったり、本当に感じたり考えたりすることを表現できなかったり、またその結果、他人や自分自身にたいしてにせの自我をあらわさなければならなかったりすることが、劣等感や弱小感の根源である。気がついていようといまいと、自分自身でないことほど恥ずべきことはなく、自分自身でものを考え、感じ、話すことほど、誇りと幸福をあたえるものはない。』
※一面的な真実を誇張している感じで、アジテーションに近いと言わざるをえない。あるいはフロムの感情が上滑りしている。
p.289
『もし個人が自発的な活動によって自我を実現し、自分自身を外界に関係づけるならば、かれは孤立した原子ではなくなる。すなわち、かれと外界とは構成された一つの全体の部分となる。かれは正当な地位を獲得し、それによって自分自身や人生の意味についての疑いが消滅する。この疑いは分離と生の妨害から生まれたものであるが、強迫的にでも自動的にでもなく、自発的に生きることができるとき、この疑いは消失する、彼は自分自身を活動的創造的な個人と感じ、人生の意味がただ一つあること、それは生きる行為そのものであることをみとめる。』
※自発性と社会の要請との辻褄が合った場合に自我が実現されるという話で、今方向性を見失っている人には目を醒ますような効果があるかもしれないが、一般論としては偏りすぎている。なぜなら外界を説得するプロセスには自発性を超えたものがつきまとうに決まっているのだから。
p.290
『自我の独自性はけっして平等の原理と矛盾しない。人間は生まれつき平等であるという命題の意味は、人間はすべて同じ根本的な人間性をあたえられ、人間存在の根本的運命を分有し、すべて同じように、自由と幸福とを求める譲渡すべからざる要求をもっているということである。』
※少し孟子を思い出す。先月ロバート・ヘアを含むサイコパス関連の書籍を続けて三冊読んだのだが、サイコパスは共通して前頭下部領域の脳の機能が著しい低位状態にあることが科学的に判明しているらしい。そのようなサイコパスだけでなく、はたして人間がすべて同じ根本的な人間性をあたえられているかどうかについて同意しかねる。
p.293
『しかし生命にたいして決定的に対立するファシストの「理想」のようなものについてはどうであろうか。あるひとびとが、他のひとびとが本当の理想にしたがっているのと同じような熱心さで、いつわりの理想にしたがっているという事実は、どのように理解できるだろうか。』
※誘導的な問いかけ方。人が生命に決定的に対立しているのに人が気づかないわけがないのだ。米国にいて祖国ドイツを眺めるフロムとは、別の条件下に(社会的・経済的に困窮したドイツ)、当時のドイツ国民はいたはずなのである。
p.296
『もしアナーキーということが、個人がどのような権威も認めないということを意味するのであれば、その答は合理的権威と非合理的権威との差別について語ったことにみいだされる筈である。合理的権威は―真の理想のように―個人の成長と発展という目標をもっている。それゆえそれは、原則として個人やかれの現実の目標と対立することはなく、かれの病的な目標と衝突するのである。』
※愛着対象を内在化できなかった個体は生きるまともな方向性を持てない。なぜなら何が合理的な目標なのかを判断する土台すらないからだ。あるいは合理性そのものが断片化したり歪んだりしている。また、特に病的な偏りがない場合でも、何が合理的な目標であるかは一般的にあらかじめ分からないことが多いだろう。
p.302
『人間がこんにち苦しんでいるのは、貧困よりも、むしろかれが大きな機械の歯車、自動人形になってしまったという事実、かれの生活が空虚になりその意味を失ってしまったという事実である。』
※欧州人が使役・搾取してきた奴隷たちはどうだったのか。また、一方で、制約的な状況下の他者が自動人形に見えてしまう人の脆弱性(or誇大感)もありえる。
p.306
『社会的性格は個人のもっている特性のうちから、あるものを抜きだしたもので、一つの集団の大部分の成員がもっている性格構造の本質的な中核であり、その集団に共同の基本的経験と生活様式の結果発達したものである。』
※或る社会階層の成員に共通した特性が見い出だせることはあるだろうが、その特徴は個人として自己のごく一部あるいはペルソナに相当している可能性が低くない。ペルソナをその人の性格構造の本質とするのは誤りだと思うが、影響がより深く浸透しているケースもあるだろうし、そういう意味での識別が必要な気がする。
p.310
『思想が強力なものとなりうるのは、それがある一定の社会的性格にいちじるしくみられる、ある特殊な人間的欲求に応える限りにおいてである。』
※ドイツの中流下層階級はナチズムに対してまず感応したのではなく、当時の困窮した社会状況にまず感応したのだ。その土壌からナチスが生まれた。第一義的に、ナチズムは社会状況の派生物にすぎない。
p.318
『それゆえ、われわれはつぎのような事実に到達する。すなわち、性格の発達は基本的な生活条件によって形成され、生物学的な固定した人間性というものは存在しないが、人間性はそれ自身一つの力学をもっていて、社会過程の進化における積極的な要因を形成している。』
※本書に限らずエーリッヒ・フロムは、人の性格形成に関して、先天的要因や乳幼児期(臨界期)の対象関係の影響にあまり立ち入らない。社会心理学者だからといって、人を主語にする場合に、それらに言及しないでは済まないはずだ。
p.320
『愛、保護、知識、物質的事物など、ひとがえたいと思うすべてのことを、自分以外の外部のものから受動的に受けとろうとする願望は、他人にたいするかれの経験の反作用として、子どもの性格のうちに発達する。もし他人との経験から恐怖心が生まれ、自己の強さの感情が弱められるならば、もし創意と自信とが麻痺させられるならば、もし敵意が発達しそしてそれが抑圧されるならば、またもし同時に、父か母が、絶対服従という条件のもとで、愛情や保護をあたえるならば、これら一連のことがらは、積極的に問題を解決する態度を失わせ、かれのすべてのエネルギーは、かれのあらゆる願望を思いがけなく実現させてくれる、外的な力を求めるようになる。』
※おそらく本書ではここが最も親子関係に接近した箇所であるが、この程度である。いわゆる魔術的援助(あるいはフロムの言うマゾヒズム)の説明でもあるが、これが当時のドイツの中流下層階級にきわめて特徴的だったためナチズムへの盲従につながっていくという理路が本書の基本骨格である。いやぁ、えーと。
p.322
『ヨーロッパの下層中産階級に典型的にみられる肛門的性格が、幼児時代の排泄と結びついた特殊な経験によって生まれると考えるかぎり、なぜある特殊な階級にだけ肛門的性格がみられるのか、ほとんど理解できなくなる。しかし、肛門的性格を、性格構造に根ざした外界との経験から生まれてくる対人関係の一形式と考えるならば、下層中産階級の偏狭とか孤独とか敵意とかいう生活様式全体が、なぜこのような性格構造を発達させたかを理解する鍵をつかむことができるのである。』
※ナチス台頭を準備したインフレで、ドイツの下層中産階級は経済・社会的に困窮したので、偏狭だったり孤独だったり敵意を持ったりしたとしても特に不思議ではない。外的な環境への適応が或る階層に属する各人に恒常的に内在化されたもののように叙述するのは適切ではない。言うまでもないが、特定の階級にだけ肛門期的性格が見られるというようなことはない。
p.326
『人間は外界の変化にたいして、自分自身を変化させることによって対処し、そしてこれらの心理的要因が、こんどは逆に、経済的社会的な過程の形成を助長する。』
※一般論としてはおっしゃるとおりです。

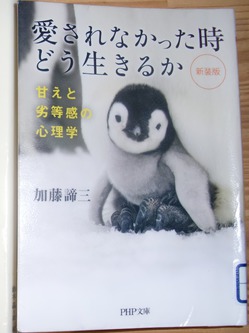
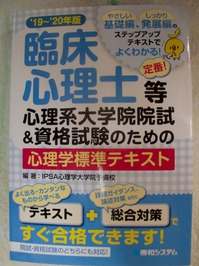


最近のコメント
purplebaby≫momoさん 不具合確認しました。 原因は調査中ですが、… (250610)
momo≫いつも活用させていただきありがとうございます。最近、「通信エ… (250610)
purplebaby≫MOさん Youtubeは、自動生成系の字幕の場合、複数の… (240325)
MO≫いつもありがたく使用させていただいています。 不具合なのか1… (240324)
purplebaby≫2023/10/16 15:49 コメント投稿者: 山田 隆… (231016)
MO≫はじめまして、便利で毎回使用させていただいていますが、1点リ… (230515)
wakamin≫もう何年も利用させていただいております。 srtだけでなく、… (230127)
sennapeng≫YouTubeの英語字幕を、ゆっくり翻訳できないかとググって… (220519)
tab≫初めて利用させて頂きました。 無料で公開してくださり本当にあ… (220507)
purplebaby≫イナチャン55さん、yosiさん、動作報告ありがとうございま… (211205)