・『いやな気分よ、さようなら―自分で学ぶ「抑うつ」克服法』 デビッド・D.バーンズ
鬱病に対する認知療法に関して述べられたやや厚めの邦訳一般書なのだが、原著は出版当時にベストセラーとなっただけでなく世界で長く読み継がれているある程度評価の定まった作品であるようだ。紹介される認知療法は先に私が入門書で読んだアドラーのやり方に酷似している感じがして、ネットで検索してみると、認知療法自体の源流には正統的にアドラー派がある旨の記述があり、そのことは今回初めて知った。そうでなくともバーンズはアドラーの名を先達として文中に出してもおり、私としては、アドラーを軽く見ていた面があったとやや反省しないでもなかった。少なくとも重度でない鬱病に対しては、認知療法は薬物による治療よりも効果的であることがほぼ実証されている。
認知療法は鬱病者に特徴的に共通する思考や認識のゆがみを矯正することによって症状をなくそうとするわけだが、バーンズが挙げるゆがみとは具体的には例えば以下のようなものだ。
(1)全か無か思考[all-or-nothing thinking]あまり内容紹介に腐心するつもりはないが、要はこれらのゆがみ(ちょっと和訳が微妙だが)を是正することが治療の近い目的となる。ゆがみの「(1)全か無か思考」はそれ以外の項目の基底をなしてもいると思うのだが、これはつまり対象関係論におけるsplittingのことであり、対象関係論の知見からそう容易には直らない場合が多々あるのではないかと思われるのだが。中庸やほどほどということが彼らにとっては心底からの苦痛でしかないのだから。それ以外本書全般に言えることだが、カラム法などにより治療が成功した例しか紹介されていないので、都合の良いところだけ並べたような不自然さが残る。
(2)一般化のしすぎ[overgeneralization]
(3)心のフィルター[mental filter]
(4)マイナス化思考[disqualifying the positive]
(5)結論の飛躍[jumping to conclusions]
①心の読みすぎ[mind reading]
②先読みの誤り[the fortune teller error]
(6)拡大解釈と過小評価[magnification and minimization]
(7)感情的決めつけ[emotional reasoning]
(8)すべき思考[should statement]
(9)レッテル貼り[labeling and mislabeling]
(10)個人化[personalization]
また鬱病の原因面については鬱病者が持つ「暗黙の仮定」を因子として幾つか挙げている。
(1)誰かに非難されると、自分がどこか間違っているような気がして惨めに感じる。バーンズはこれら鬱病者に特徴的な暗黙の仮定を非論理的なものだとして強く退ける。例えば、誰にも愛されていなくても幸福と言えないわけではないとか、仕事の実績は人間の価値とはまったく関係ないとか主張する。このような主張は一般常識あるいは通念に対する偏頗なアンチテーゼの提出であり、以前私が別の認知療法に関する本を読んだ時に「何だか詭弁に近い」と思った所以でもあるのだが、微妙なところだと改めて思わないではいられなかった。例えば、詐欺会社で働く社員がどれだけ「有能」だとしても人としての価値は高くないだろうということを理由に(バーンズ自身はヒトラーを例示しているが)、どのような仕事の実績も人間の価値とは直接には関係がないと結論付けるのはほぼ詭弁であるように私には思える。社会に寄与する一般的な仕事上で何かすばらしい業績を挙げることは、常識的な意味において、共通して尊敬されるべきことであり万人が求める状態であるに変わりはないはずだ。また他人から愛情や好意を受けることが殆ど普遍的な価値であるということが、一人でアイスクリームを食べたりすることの卑近な幸福感を引き合いに出すことにより、同次元で相対化されるものではないはずだ。同じく愛情関係に付随するしがらみの面倒を過度に強調することも作為的だ。もし自分の主張に反対するならそれらが絶対に価値であり幸福であることを厳密に証明せよ、とバーンズは言うが、これは悪魔の証明の要請に近い。
(2)本当に完璧な人であれば愛されるはずである。もしひとりぼっちだったとしたら、寂しく惨めになる覚悟を決めなくては。
(3)人間としての価値は、自分の成し遂げてきたことに比例する。
(4)もし完全に行わなかったら、感じなかったら、あるいは振る舞わなかったら、私は失敗したことになる。
まあ、それら普遍的だと信じられている価値や幸福を「絶対視して」追わないような生き方に何とか軟着陸させるために、敢えて詭弁・強弁を弄していると好意的に解釈すればそう出来るかもしれない。バーンズ自身の表現も揺れている部分があると思う。
私は色々疑念を持ちながらも、同時に幾つか別のことを考えていた。そのうちの一つは「自我の芯」とでも言うべき観念についてのものだ。社会において普遍的な価値観だとしても、それらを過剰にも「絶対視」「完全視」すれば、自らががんじがらめになってしまうのは必然だ。あるいはそれらを失った時に「この世のすべて」を失ったように思い過ごしてしまうのは必然だ。自我の芯は、どのような社会的条件にも支配されないで、生命本来のエネルギーを諸活動にそのまま供給し続け得る基礎領域だ。善悪の彼岸にあって、常に単独者としての最低限の活動を保障する。
私は世俗的な価値観の普遍性を安易に否定すべきではないと思う。全体主義のような価値の押しつけが社会の側からあるとしたら行き過ぎだと思うが、それがある程度普遍的な価値であるというのは群盲による何かの思い違いではない。科学的に証明し得ないとしても経験的・歴史的に知られた普遍的テーゼなのだ。問題はそれとの共存の仕方にこそあるはずだ。世俗的な価値によって侵されざる領域、自我の芯を持つことだ。
もう一つ書いておこうと思うのは、ネット上で散見される「鬱=甘え」論の正体に関してだ。もちろんこれは鬱がそのまま甘えという意味ではないだろう。鬱とは気分が落ち込むことなのだから。おおよそ鬱の原因が甘えだという主張なのだろうと思う。
例えば、似たような悲劇が諸個人に降りかかって、しばらくしたならその悲しみから立ち直る人物と、落ち込んだ状態を不必要にぐずぐず長引かせる人物がいるとする。前者を健全かつ自立的で、後者を当人には過分な幻想に固執する甘えた人物だと短絡する観察者がありうる。だが、外形的に後者に似ているかもしれない鬱病者は、先述のように人生の早期から体に染みこんだ全か無か思考(=splitting)によって世界を把握しているために、元々常に気が晴れることがないのであり、同じ理由で特定の悲劇に対するリアクションも抑鬱や無気力が過剰に重くなりその期間も長引くことにもなっているのだ。また少なくともメランコリー親和型の場合、自分だけで苦悩を処理しようとする傾向が共通してあるはずで他人に頼ろうとすることなど普通よりむしろ少ないはずだ。仮に気分が憂鬱だと周囲に表明したとしても、殆どは単に自分の現状を説明しているだけであり、当人としては特に弱音を吐いているわけでも助けを求めているわけでもないと考えられる。ただし、内的に危急の状態にあるか、他の人格障害に伴う抑鬱が鬱病にまで発展したような場合、投薬によって不安定になっているような場合、自己に積極的にストレスを与える攻撃者が存在するような場合には、他者に対して単なる説明ではない何らかの意思表示がなされる場合があるかもしれない。憂鬱だと言われれば周囲は心配してみせるのが日本社会の建前であって、往々にして、表明は真剣さを欠いたまたは過分なSOS(=甘え)として映り誤解と反感を買うことがあるかもしれない。
鬱病者は、元々の認知の仕方や感受性のあり方が普通と違うわけで、それにより妥当なリアクションが出来ないことが病の本質なのである。従って、鬱病でない人は鬱病者の苦悩に原理的に共感し得ず、不適切か不自然な苦悩にしか映らない。あるいは苦悩そのものがあるのかどうかも甚だ疑わしい(演技ではないか等)ということになりかねない。
この、自分と基本的な素地が異なったタイプが世の中にいるということが想定できないタイプがまた別にある。自分の無知や有限性を認められないタイプと言い換えても良いが、自己愛人格などがそうである。加えてネガティヴな対象を積極的に排除したがる傾向もあると思うので、自己愛人格は鬱病者に吸い寄せられるようにして攻撃することになるだろう。
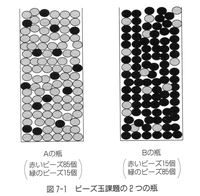
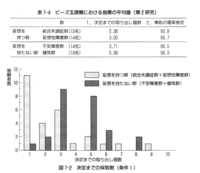

最近のコメント
purplebaby≫momoさん 不具合確認しました。 原因は調査中ですが、… (250610)
momo≫いつも活用させていただきありがとうございます。最近、「通信エ… (250610)
purplebaby≫MOさん Youtubeは、自動生成系の字幕の場合、複数の… (240325)
MO≫いつもありがたく使用させていただいています。 不具合なのか1… (240324)
purplebaby≫2023/10/16 15:49 コメント投稿者: 山田 隆… (231016)
MO≫はじめまして、便利で毎回使用させていただいていますが、1点リ… (230515)
wakamin≫もう何年も利用させていただいております。 srtだけでなく、… (230127)
sennapeng≫YouTubeの英語字幕を、ゆっくり翻訳できないかとググって… (220519)
tab≫初めて利用させて頂きました。 無料で公開してくださり本当にあ… (220507)
purplebaby≫イナチャン55さん、yosiさん、動作報告ありがとうございま… (211205)